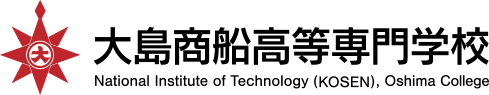- 大島丸
【大島丸代船建造 プロジェクト】エピローグⅠ
みなさんこんにちは。
いよいよこの日がやってきました!!
お待たせしたね。
3月13日に生まれ故郷の三菱造船下関工場で引渡しを受けたことは、知ってのとおり。
はい、新大島丸は強運の持ち主ですから、雨予報が快晴に変わりました。
沢山の関係者に見送られたんですよね。

(三菱造船から出港の様子)
でも、新桟橋に初入港したのは翌日じゃなかったですか。
桟橋工事が直前まで行われていたから、調整していたんだ。
その代わりに下関港に着岸して、建造に携わって頂いた三菱造船の家族の方に船内を見学して貰ったんだ。
お父さんが造った船だから、誇らしかったでしょうに。
そうだね。本船建造に関わった皆さんにとって、自慢のフネになると嬉しいね。

(引渡し当日、下関港岬之町)
新大島丸が着桟して、学校から見える景色が変わりました。
桟橋をかける角度が変わったから、船型がしっかり確認できるようになった。
なんといっても、シュッとした煙突の上のマストがカッコいいです。
これから、君たちの心に刻まれていくことになるだろうね。


ピカピカだから、桟橋の文字が船体に写ってるじゃないですか。
ペイントにはウレタン塗料を採用したからね。光っているだろう。
乗船口が高くなったので、並行に乗込めるように乗船タワーを設置したんだ。
ほんとだ、安心感抜群ですね。
桟橋も新しくて大きいんですけど・・、早く乗船しましょうよ。
それでは船内ツアーと決め込みますか。
大島丸Ⅳ世にようこそ。
船尾の舷門口から乗船すると、そこは船尾スタンバイデッキだ。
フェリーの乗船口みたいですね。
乗船タワーにはスロープもあるから、体の不自由な方も乗船できる。

船尾の係船甲板も広いですよね~。
一班10人での実習でも、余裕があります。

(上甲板右舷側通路)
なんと!ストレートで長い通路が、まるで客船みたいじゃないですか。
これはC/O(一等航海士)が最後まで譲らなかった設えなんだ。
後から変更できないから、早い段階で方針を固めておくことが大切なことがわかるだろう。装備品の配置を考えるだけが工夫じゃないんだ。
わかります。奥行が出て長く見えますもんね。
それに幅があるから、行き違いも問題ありません。
入口は下部も可動式になっているから、コーミング(防水壁)がないだろう。
そうだ、それで入る時に違和感がなかったんですね。
君たち学生は、左舷側から入って、すぐに洗面所で手洗いとうがいだ。
心得ております。まだまだ感染症対策は必要ですからね。

右舷側通路には、病室と多機能トイレがあるんですね。
桟橋から車椅子で入ることができるんだ。
このトイレは普段使っちゃダメなんですか?
電車やバスのゆずりあいの席と一緒で、この設備を必要とする人が居る時にゆずってあげればいいんだ。
それ以外の時は、使ってくれて構わない。

入口には両舷とも教員室を配置して、しっかり学生を見守ることができる。
安心ですね。教員室なのに、階段の足形が可愛いです。
そして、舷側(げんそく)側は、船首に向かって学生居住区が続くんですね。
ブルー/オレンジ/ブラウン/ベージュ、どの部屋があたるかなあ?
楽しみです。

このオレンジラインが女子エリアの目印でしたよね。
通路以外に余裕もあって、閉塞感を感じませんよ。
そう言って貰えると嬉しいね。

これまでは、どうしても人数の少ない女子の居住区を船奥や狭いところに追いやる配置と成らざるを得なかったから、発想を転換してここをメインに考えてみたんだ。
ちょっと騒いでもわかんないかな?
そこは船乗りらしく、節度を持ちなさい。
はい。パウダールームも完備されています。
Mさんは実習の邪魔にならないよう、いつも髪を纏めていたから、乗船中でもセットがやりやすいように、三面鏡を設置しているよ。
今まで部屋でバタバタやってましたからね。

あ、女子トイレの個室が3つに増えていますから、さっきの多機能トイレを使うことはないのか。
そうだね。多機能トイレは、多様化の時代に併せて、誰でも入ることができる「みんなのトイレ」として使ってくれるといいね。
パウダールームにはドラム式の洗濯乾燥機がありますよ。
乗船している学生に平等に船内生活を送って貰うのが、コンセプトだからね。
シャワーブースもとっても清潔そうです。
このサイズの船では、スペースがないから個室の採用例は少ないんだ。
掃除のしやすい壁を張って、床には乾きやすい素材を採用してもらった。
ささっと汗を流すだけじゃなくって、イヤなことも流してしまえそうです。

狭い船内でも男子トイレ内の小便器が直接見えないようにクランクを設けている。
ほんとだ、これまでなんとはなしに気を使っていたので、助かります。
ギャレーが学生ホールへの喫食動線となっているのがわかるだろう。
盛付けられたお皿をとって、学生ホールへ行く流れができていますね。
そして、私たちの教室となる学生ホールですね。
机上実習、授業、食事、だんらんと、フル活用してもらいたいね。

ドックでの青い養生が外れると、とても落ち着いた雰囲気ですね。
それは、それは、学習がはかどるだろうて。
ええと・・、そうですよね。
世界時計もあるんですね、普段の授業もここで受けたいです。
望むところだ。
今後は、できるだけ本船の設備を使うつもりだから、準備しておきなさい。
(言うんじゃなかった)
隣の乗組員食堂なんて、ちょっとしたカフェみたいです。
当然厨房設備も新設されているし、お皿やコップもこれまでのものとは変えたよ。
お昼ご飯が、おしゃれなランチになっちゃいます。
でも、これだけの設えを造るって大変でしょうね。

(YFF特製 スマホ立て)
私たち船員は、航海のために使う装備品のことは知っていても、こんな設えには詳しくないからね。
すると、フィクサーがいるわけですね。
笑)言い方。内艤設計との綿密な打ち合わせだ。
初見の挨拶で、「内装の設えで、学生にアッと言わせましょう」と持ち掛けると、力強く「そうしましょう」と答えてくれたからね。
ほんとに驚きました。
実際に工事にあたったYFFの方々の腕も見逃しちゃいけない。
そうですよね。まんまと術中にハマっちゃいました。
これまでにない取組みだったから、設計や工事も大変だったんだ。
あちこちで、「こんな練習船造ったことないわ」って声が聞こえていたよ。
練習船初だらけですもん。
でも、これからは、当たり前になってくるのかも。
船内ツアー前半戦は、このくらいにしておこうか。
まだ、乗組員の部屋を見てないですよ。
本船のウリはそこじゃないからね。
最後まで焦らしますよね。
しょうがないので、ちょっとだけ待ちます。